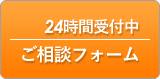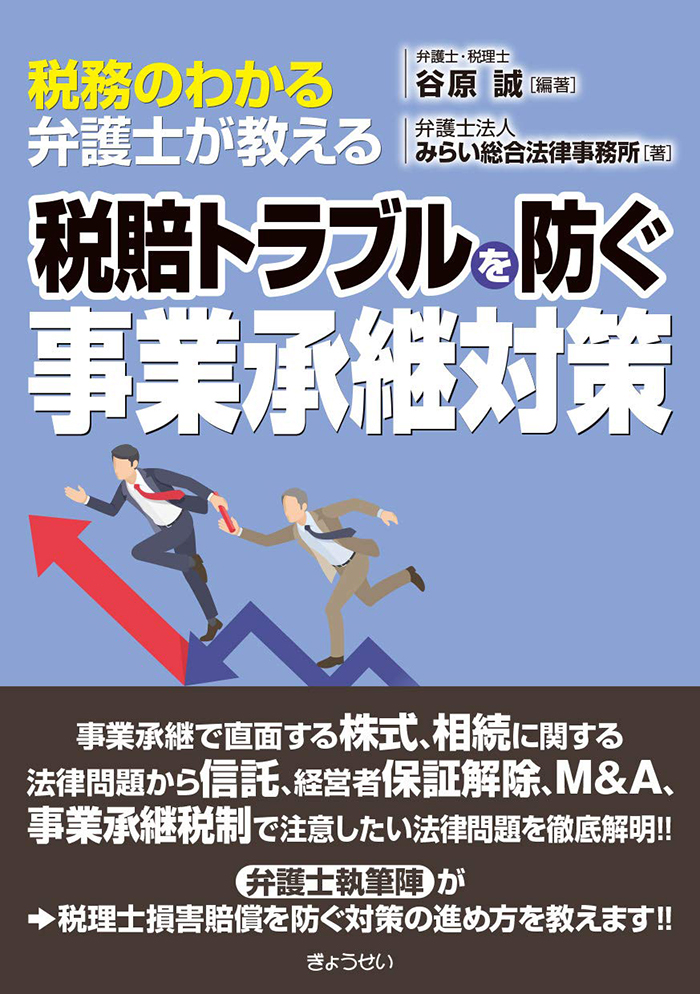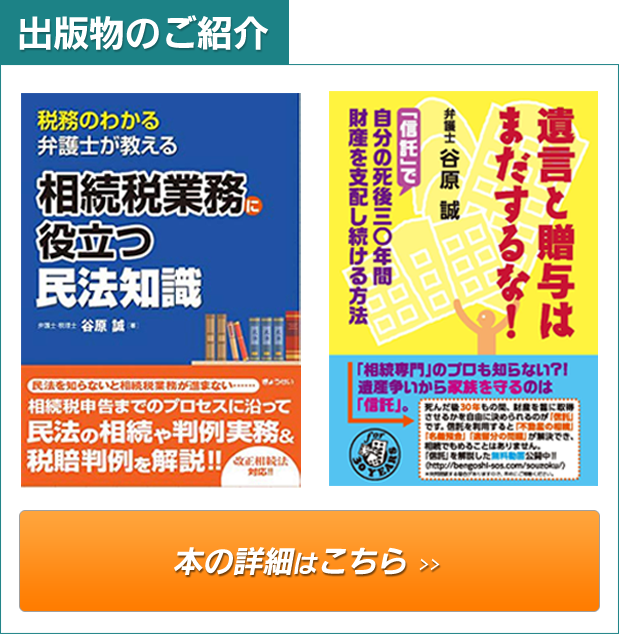遺留分の計算
遺留分の基礎となる財産
遺留分の基礎となる財産の計算は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除することによって行います(民法第1029条1項)。
「相続開始の時において有した財産」は、積極財産のことであり、遺贈や死因贈与の目的とされた財産も含まれます。
条件付の権利または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従ってその価額を決めることになります(同条2項)。
計算式にすると、次のようになります。
相続開始時の積極財産+贈与-債務=遺留分算定の基礎となる財産
「贈与した財産」については、特別受益として贈与した財産と、その他の一般贈与した財産とで取扱が異なります。
まず、一般贈与の場合には、相続開始前の1年間にしたものに限って遺留分算定の基礎財産に算入するのが原則です。
しかし、贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与であっても、遺留分算定の基礎財産に算入することになります(民法第1030条)。
ここで、「遺留分権利者に損害を加えることを知って」というのは、●贈与当時の財産状態で遺留分を侵害するという事実の認識と、●将来においても財産が増加し、その結果、遺留分が充足されることはありそうにないという予見、が必要とされています。
これに対し、相続人に対する特別受益として贈与された財産については、贈与時期にかかわらず、全て遺留分算定の基礎財産に算入することになります(民法第1044条、903条)。
ただし、最高裁平成10年3月24日判決(民法百選Ⅲ93)は、「相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続などの関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情があるときは減殺の対象とならない」としています。
この点も改正されています。2019年7月1日以降に開始される相続については、次とのとおりとされます。
(特別受益の場合)
①特別受益に該当する贈与であり、
かつ、
②相続開始前10年間にされたものに限り、
その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入することとされます。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、10年より前にされたものであっても、遺留分算定のための財産の価額に算入することになります。
(一般贈与の場合)
相続開始前の1年間にされたものに限り、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入するとされます。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、1年より前にされたものであっても、遺留分算定のための財産の価額に算入します。
特別受益を受けた相続人が、相続放棄をした場合の持戻しは、どうなるでしょうか。
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります(民法第939条)。
したがって、相続人としての特別受益はなくなり、その観点からの持戻しはなされないこととなります。
そこで、この場合には、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与かどうかが検討されることになります。
相続開始前にされた贈与財産について、いつの時点での価額を遺留分算定の基礎財産に算入するかについて、多数説は、相続開始時の貨幣価値に換算されるとされています。
特別受益として贈与された財産を遺留分算定の基礎財産に加える場合、それが金銭である場合には相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価する、とした判例として、最高裁昭和51年3月18日判決(民集30巻2号111頁)があります。
遺留分侵害額の計算
遺留分の基礎となる財産を計算したら、個別に遺留分権利者の遺留分侵害額を計算することになります。
この計算方法については、最高裁平成8年11月26日判決(民法百選Ⅲ90)は、遺留分算定の基礎となる財産に、民法第1028条所定の「遺留分の割合を乗じ、複数の遺留分権利者がいる場合は更に遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、遺留分権利者がいわゆる特別受益財産を得ているときはその価額を控除して算定すべきものであり、遺留分の侵害額は、このようにして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合はその額を控除し、同人が負担すべき相続債務がある場合はその額を加算して算定する」と判示しています。
民法第1028条所定の遺留分の割合は、遺留分権利者全体に遺されるべき相続財産全体に対する割合であり、総体的遺留分率といい、次のようになっています。
①直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の相続財産の3分の1
②その他の場合は被相続人の相続財産の2分の1
前述の最高裁の判決文を計算式にすると、次のようになります。
遺留分算定の基礎財産×(総体的遺留分率×遺留分権利者の法定相続分の割合)-当該遺留分権利者の特別受益額-遺留分権利者が相続によって得た財産の額+遺留分権利者が負担すべき相続債務の額=遺留分侵害額
相続人に対する遺贈が遺留分減殺請求権の対象となる場合に、受遺者も遺留分を有している場合があります。
この場合に、遺贈の全部が遺留分減殺請求権の対象となると、受遺者の遺留分が侵害される結果となってしまいます。
そこで、このような場合は、遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが減殺の対象となる価額となります(最高裁平成10年2月26日判決、民法百選Ⅲ95)。
特別受益としての贈与について持戻し免除の意思表示がされていた場合において、当該贈与が遺留分減殺請求権の行使により減殺されたときは、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与にかかる財産の価額は、遺留分を侵害する限度で遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される、とした判例があります(最高裁平成24年1月26日判決、民法百選Ⅲ96)。