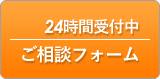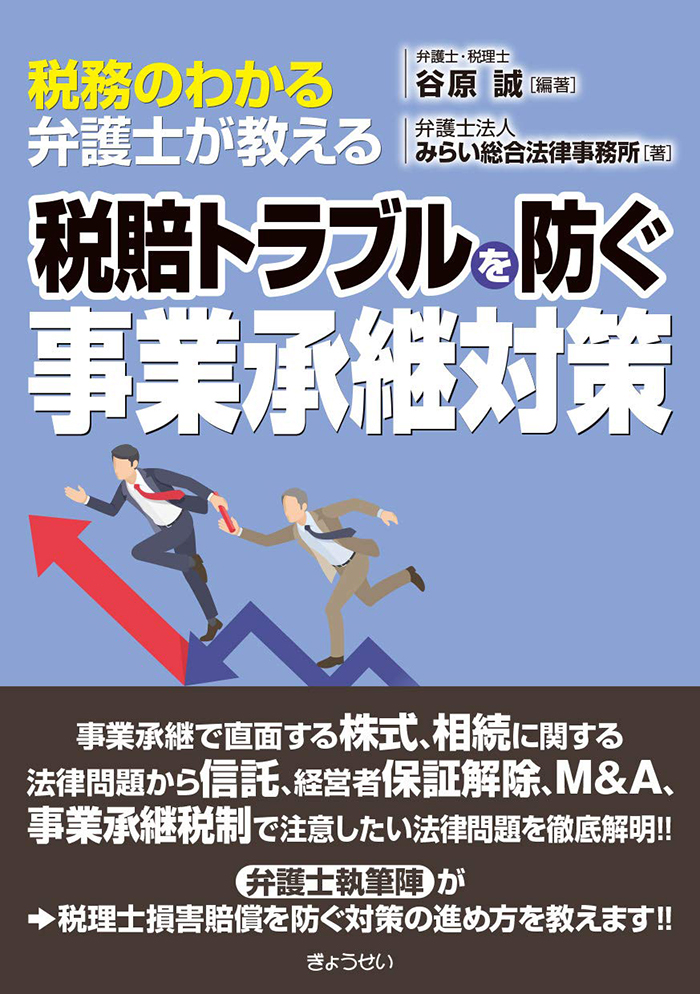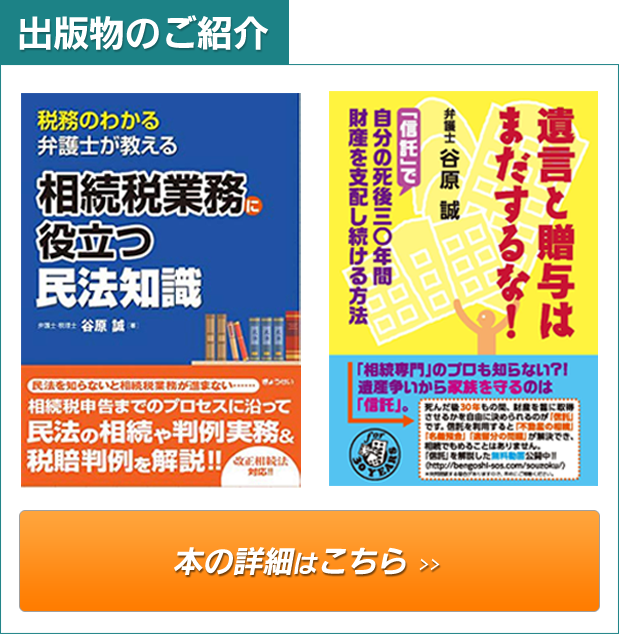特別受益とは?
目次
特別受益とは
被相続人から共同相続人に対して、①遺贈され、または②婚姻や養子縁組のために贈与され、もしくは③生計の資本として贈与された財産を「特別受益」といいます(民法第903条1項)。
「婚姻若しくは養子縁組のため」とは、婚姻のための持参金、支度金、結納金、挙式費用や養子縁組のための支度の費用等が含まれることになります。
ただし、その価額が少額で、被相続人の資産および生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合は特別受益とならないと解されています。
「生計の資本としての贈与」とは、生計への資金援助や住むための建物の贈与などが挙げられますが、広く生計の援助となる財産上の給付で、扶養義務の範囲を超えるものが含まれます。
相続人の債務を被相続人が肩代わりして支払い、その求償をしなかったことが、「生計の資本としての贈与」に該当することもあります(高松家庭裁判所丸亀支部平成3年11月19日審判・家裁月報44巻8号40頁)。
父の相続にあたって子が母から法定相続分を譲り受けた件について、相続分が財産的価値を有すること、無償で相続分の譲渡がなされたことなどから、「生計の資本としての贈与」として、特別受益に該当するとした裁判例があります(東京高裁平成29年7月6日判決、判例時報2370号31頁)。
特別受益があったときは、相続分の前渡しと評価され、相続の際に、特別受益財産を相続財産に計算上持戻して具体的相続分を計算することになります。
これを「特別受益の持戻し」といいます。
ただし、被相続人は、共同相続人の遺留分を侵害しない限度で、特別受益の持戻しを免除することができます(民法第903条3項)。
また、2019年7月1日以降にされた遺贈または贈与については、持ち戻し免除の推定規定が適用されます。
これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する、というものです。
持戻しの対象となるのは、共同相続人に対する贈与や遺贈に限定されます。
相続人が相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、相続放棄をした相続人に対する贈与や遺贈は持戻しの対象にはなりません。
特別受益とされた財産について、贈与時の価額と相続開始時の価額に差があるときは、特別受益とされた財産の価額は、相続開始時の時価に換算することになります(最高裁昭和51年3月18日判決、判例時報811号50頁)。
特別受益の具体例
被相続人から共同相続人に対する贈与や遺贈は、比較的広く特別受益と認定される傾向にあります。
以下には、過去の裁判例において、贈与の全部または一部が特別受益と認められなかった事例を紹介します。
(一)長﨑家裁島原支部昭和40年11月20日審判(家裁月報18巻5号75頁)
被相続人が株式や債権を妻に贈与したことについて、被相続人が妻の実家から金融を受けていたこと、被相続人が胃癌のため死期のいよいよ迫るのを覚悟し、永年共に農業に従事し農地など相続財産の維持に協力した労に報いるためであるとして、生計の資本としての贈与と認めませんでした。
(二)神戸家裁姫路支部昭和49年8月10日審判(家裁月報27巻6号80頁)
被相続人が妻に対して生前に1,000万円を贈与したことについて、妻は被相続人の死亡の20年以上前からタイプ学院を経営し、その純益の相当部分を夫婦の生活費に入れ、被相続人の財産の減少を防止するにつき若干の寄与があったこと、被相続人の身の回りの世話について妻に相当の負担がかかっていたこと、から、1,000万円のうち5割は家計に対する特別寄与分の清算と老齢の夫に対する長年の看護の労に報いる趣旨の贈与と認め、残額の500万円のついてのみ生計の資本のための贈与と認めました。
(三)盛岡家庭裁判所一関支部平成4年10月6日審判(家裁月報46巻1号123頁)
被相続人が養子である相続人に不動産を生前贈与したことについて、相続人がほとんど一人で家業である農業に従事する一方、工員として稼働して得た収入で被相続人および家族の生活を支えていたこと、被相続人の療養看護に勤めたこと、から、被相続人の貢献がなければ財産の維持はできなかったことから、被相続人の贈与は、それらの貢献への感謝と貢献に報いる気持ちで行ったものであり、特別受益にあたらない、としました。
特別受益とされた場合の計算式
共同相続人に対する贈与や遺贈が特別受益とされた場合、各共同相続人の具体的相続分は、次のように計算されることになります(民法第903条1項)。
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、特別受益たる贈与の価額を加算する(みなし相続財産)。
なお、この場合、債務は控除しない。
(計算式)
相続開始の時において有した財産の価額+贈与価額=みなし相続財産
②①のみなし相続財産に、当該共同相続人の相続分を乗じる。
(計算式)
みなし相続財産×各共同相続人の相続分
③②の金額から、当該共同相続人の受けた贈与・遺贈の価額を控除する。
(計算式)
②の相続分-当該共同相続人の受けた贈与・遺贈=具体的相続分
具体例で説明します。
被相続人の相続財産 3000万円
相続人 子A・B・C
被相続人からAに対し、生前に2000万円の特別受益たる贈与があり、被相続人からBに対し、生前に1000万円の生計への援助としての贈与があった。
(計算式)
①3000万円+2000万円+1000万円=6000万円(みなし相続財産)
②6000万円×1/3=2000万円(各自の相続分)
③A 2000万円-2000万円=0円
B 2000万円-1000万円=1000万円
C 2000万円-0円=2000万円
以上より、具体的相続分は、Aは0円、Bは1000万円、Cは2000万円となります。
特別受益と相続税
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産については、相続時精算課税適用者が、本制度を適用した贈与者の相続に際し、相続または遺贈により財産を取得したときは、相続時精算課税の適用を受けた特別財産については相続税の課税価格に加算します(相続税法第21条の15第1項)。
また、当該相続に際し、財産を取得しなかった場合は、相続時精算課税の適用を受けた特別受益財産については、相続または遺贈により取得したものとみなされます(相続税法第16条1項)。
しかし、相続時精算課税制度の適用を受けていない場合は、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産は、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続税の課税価格に加算することとされています(相続税法第19条)。
ただし、特定贈与財産は除きます。
ここで、特税贈与財産とは、贈与税の配偶者控除(相続税法第21条の6)の対象となった受贈財産のうち、その配偶者控除に相当する部分(最高2000万円)のことです。
この結果、相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税価格に加算されるものについては、その年の贈与税の課税価格には算入しないこととなります(相続税法第21条の2第4項)。