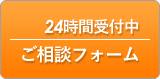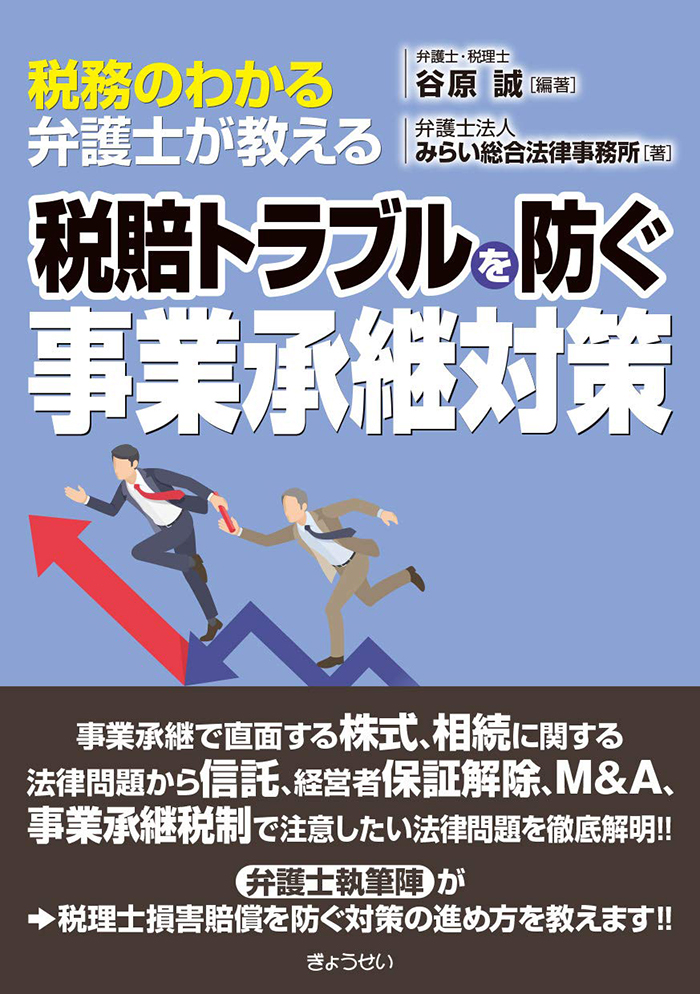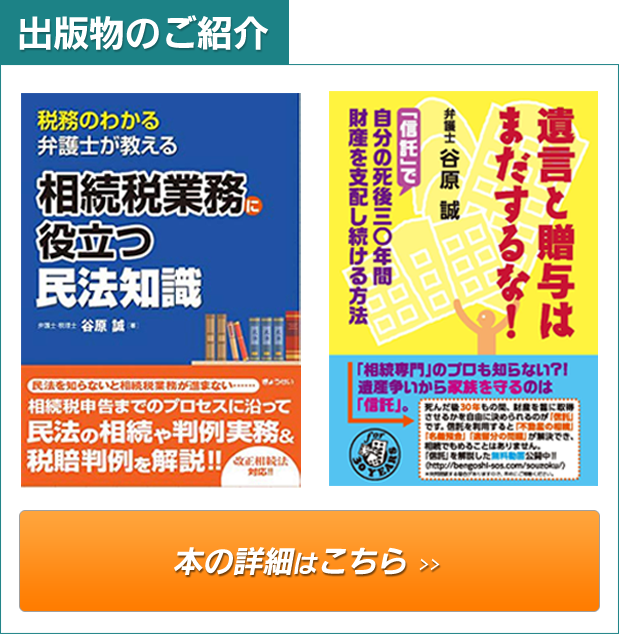相続の承認・限定承認・放棄とは?
相続が開始した場合、相続人は、被相続人の財産を承継するかどうか、決めなければなりません。
相続財産は必ずしもプラスの財産だけではなく、マイナスの負債も相続の対象となりますし、相続人が相続による財産承継を望まない場合もあります。
そこで、相続の開始があったときは、相続人は、相続の仕方について、3つの方法を選択することができます。
その3つとは、①単純承認、②限定承認、③相続放棄、です。
目次
単純承認とは
相続人が単純承認をすると、被相続人の権利義務を無限に相続することになります(民法第920条)。
相続人が単純承認する旨の意思表示をすると、単純承認の効果が発生しますが、次の3つの場合には、承認の意思表示をしなくても、単純承認をしたものとみなされます。
なお、単純承認は、相続開始後でなければすることができません。
①相続財産の全部または一部の処分(民法第921条1項)
相続人が自己のために相続が開始した事実を知り、又は確実に予想しながら、相続財産を処分したときは、単純承認したものとみなされます。
債権の取り立てや代物弁済は、処分したときにあたります。
また、賃貸不動産の賃料振込名義を変更することも、処分行為とされています。
ただし、保存行為や短期賃貸をすることは、単純承認にはあたりません(同項但し書き)。
遺産から葬儀費用を支出する行為は、処分行為にはあたらないとした、大阪高裁平成14年7月3日決定(家月55巻1号82頁)があります。
相続人が有効に限定承認または放棄をした後に相続財産を処分しても、単純承認にはあたりません。
②熟慮期間の経過(民法第921条2項)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認または相続放棄をすることができます(民法第915条1項)。
これを熟慮期間といいます。
熟慮期間は、相続人が承認・放棄をするにあたり、相続財産の内容を調査して、いずれにするかを考慮する余裕を与えようとするものです。
熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、死亡の事実を知ったことに加えて、それによって具体的に自分が相続人となったことを知ったときです。
ただし、最高裁昭和59年4月27日判決(百選Ⅲ75)は、次のように判示しています。
「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められる時には、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」
相続人が数人いる場合には、熟慮期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知ったときから格別に進行します(最高裁昭和51年7月1日判決・家裁月報29巻2号91頁)。
相続人が未成年者または成年被後見人であるときは、熟慮期間は、その法定代理人が未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った日から起算します(民法第917条)。
相続人が熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは、相続人は単純承認したものとみなされます。
③相続財産の隠匿等(民法第921条3項)
相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、ひそかに消費したり、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認したものとみなされます。
ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をしたときは、単純承認の効果は生じません。
単純承認の効果
一度、単純承認をすると、熟慮期間内であっても撤回することはできなくなります(民法第919条1項)。
ただし、制限行為能力者の場合、詐欺・強迫など意思表示に瑕疵がある場合、後見人が後見監督人の同意なく承認したときは、取消すことができます(民法第919条2項)。
単純承認の取り消しは、追認することができるときから6ヵ月間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続の承認から10年を経過したときも同じく消滅します。
また、相続の承認の意思表示に錯誤(民法第95条)などの無効原因があるときは、無効を主張することができます。
相続放棄とは?
相続人が、被相続人の財産を取得することを望まない場合には、相続放棄をすることになります。
相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法第882条)。
しかし、相続開始によって生じた相続の効果を、全面的・確定的に消滅させることができます。
その行為を相続放棄といいます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して申述することによって行います(民法第938条)。
相続放棄は、相続開始後でなければすることができず、相続開始前にしても効果を発生しません。
家庭裁判所の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内にしなければなりません(民法第915条1項)。
これを熟慮期間といいます。
この熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、死亡の事実を知ったことに加えて、それによって具体的に自分が相続人となったことを知ったときです。
ただし、最高裁昭和59年4月27日判決(百選Ⅲ75)は、次のように判示しています。
「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められる時には、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」
相続人が数人いる場合には、熟慮期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知ったときから格別に進行します(最高裁昭和51年7月1日判決・家裁月報29巻2号91頁)。
相続人が未成年者または成年被後見人であるときは、熟慮期間は、その法定代理人が未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った日から起算します(民法第917条)。
相続放棄の効果
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。
そして、相続放棄があった場合、相続放棄をした者の子は、代襲相続することはできません。
相続放棄は代襲原因とされていないためです(民法第887条2項)。
相続放棄には絶対効があり、何人に対しても、登記等なくして相続放棄の効果を対抗できることとされています(最高裁昭和42年1月20日判決・民法百選Ⅲ72)。
父が死亡して相続が開始し、相続人である長男が承認や放棄等をする前に死亡して、長男に子がいるような場合を「再転相続」といいます。
この再転相続の場合、長男の子の相続放棄に関しては、次のようになります。
最高裁昭和63年6月21日判決(民法百選Ⅲ76)です。
①長男の子が長男の相続に関して相続放棄した場合は、父の相続に関して承認も放棄もできない。
②長男の子が長男の相続に関して相続放棄していないときは、父の相続に関して放棄することができ、かつ、長男の相続に関して承認または放棄をすることができる。
なお、相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法第940条)。
相続分の放棄
相続放棄と異なるものとして、「相続分の放棄」があります。
これは、共同相続人が自分の相続分を放棄することです。
方式は問いませんが、書面ですることにより、証拠化する方がよいでしょう。
相続分の放棄は、遺産分割がなされるまでの間は、いつでもできます。
相続分の放棄は、相続放棄と異なり、相続人の地位を失うものではありません。
したがって、相続債務を免れるわけではありませんので、注意が必要です。
また、相続放棄がなされた場合と相続分の放棄がなされた場合では、他の共同相続人の相続分に与える影響に違いが出てきます。
具体例で説明します。
被相続人に妻、長男、次男の共同相続人がいるとします。
法定相続分は、妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1です。
ここで、次男が相続放棄をすると、次男は、初めから相続人ではなかったことになります。
そうすると、相続人は、妻と長男になりますので、それぞれの相続分は、2分1ずつ、ということになります。
しかし、次男が相続分の放棄をした場合には、次男の相続人の地位は失われません。
したがって、法定相続分は、妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1です。
ここで、次男が相続分の放棄をして、自分の相続分を放棄しますので、次男の4分の1が、妻2分の1と長男4分の1の比率に応じて配分されます。
そうすると、
妻1/2(2/4):長男1/4=2:1の比率です。
相続分率は、2/3:1/3です。
次男の1/4を、これに配分すると、
妻2/3×1/4=1/6
長男1/3×1/4=1/12
これを、元の法定相続分に加算すると、
妻1/2+1/6=4/6=2/3
長男1/4+1/12=4/12=1/3
したがって、次男が相続分の放棄をした場合には、妻の相続分が3分の2、長男の相続分は3分の1となります。
限定承認とは?
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する行為です(民法第922条)。
限定承認は、家庭裁判所に対して申述することによって行います(民法第924条)。
家庭裁判所の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
限定承認は、相続開始後でなければすることができず、相続開始前にしても効果を発生しません。
また、限定承認は、単独ですることができず、相続人全員が共同してしなければなりません(民法第923条)。
包括受遺者がある場合は、包括受遺者も共同してする必要があります。
限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内にしなければなりません(民法第915条1項)。
これを熟慮期間といいます。
この熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、死亡の事実を知ったことに加えて、それによって具体的に自分が相続人となったことを知ったときです。
ただし、最高裁昭和59年4月27日判決(百選Ⅲ75)は、次のように判示しています。
「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」
限定承認の効果
限定承認をすると、相続人は被相続人の権利義務を全て承継しますが、相続債務に関しては、相続した積極財産の限度でのみ弁済の責任を負うことになります。
限定承認をした相続人は、相続財産を精算することになります。
まず、限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならなくなります(民法第926条1項)。
限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、全ての相続債権者および受遺者に対し、限定承認をしたことおよび2ヵ月以上の一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません(民法第927条1項)。
限定承認者に知られておらず、かつ、この期間内に申出をしなかった相続債権者や受遺者は、法に従った弁済をした後の残余財産についてのみその権利を行使することができます(民法第935条)。
限定承認者は、相続債権者や受遺者から請求があっても、公告した期間の満了前には、弁済を拒むことができます(民法第928条)。
公告した期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に申出のあった相続債権者や知れている相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済しなければなりません。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできません(民法第929条)。
この弁済は、当該債権が弁済期前であっても弁済しなければならず、債権が条件や不確定期間にかかっているものについては、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済しなければなりません(民法第930条1項、2項)。
限定承認者は、相続債権者に対して弁済した後でなければ、受遺者に対して弁済することができません(民法第931条)。
金銭以外の相続財産があり、相続債権者や受遺者に対して弁済するにあたり、相続財産を換価しなければならない場合は、限定承認者は、競売に付して換価しなければなりません(民法第932条)。
限定承認をした相続人が不動産を死因贈与され、所有権移転登記をした後に、相続債権者が差押登記をした場合に、相続人は所有権移転登記をもって相続債権者に対抗できるか、が争われた事案があります。
この事案において、最高裁平成10年2月13日判決(民法百選Ⅲ77)は、「不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記より先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない」と判示しています。
所得税法上、相続人が限定承認をした場合は、被相続人が相続時点において資産を譲渡したものとみなされます(所得税法第59条1項1号)。
したがって、相続があったことを知った日から4ヵ月以内に準確定申告が必要となります。
これにより、相続人は、相続開始時点において、その資産を時価で取得したものとみなされることになります。
これは、熟慮期間を伸長した場合も同じです。
相続開始から4ヵ月を経過した後に準確定申告をした事例において、延滞税を課した裁判例として、東京高裁平成15年3月10日判決(TAINZZ253-9302)があります。